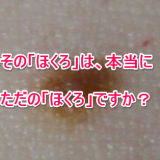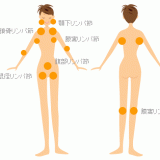お金が貯まらないのは、「あれば使ってしまう」からです。
これでは、将来に必要な資金を貯めることはできません。
そこで、今回紹介するのが「財形貯蓄」という制度です。
給料からの天引きで貯金できるので、いつの間にかお金が貯まるおすすめの方法です。
財形貯蓄は生活安定のために作られた
財形貯蓄は、1971年に制定された「勤労者財産形成促進法」に基づいて設けられた「勤労者財産形成貯蓄」の略称です。
勤労者財産形成促進法は「勤労者の計画的な財産形成を促進することで勤労者の生活の安定を図り、国民経済の健全な発展に寄与する」ことを目的に制定された制度です。
簡単に言えば、労働者の生活を安定させて、たくさん働いてもらおう!という制度です。
福利厚生制度のひとつとして導入している会社の勤労者だけが利用できます。
つまり、雇用されている会社員、公務員、パートタイマー、アルバイト、派遣社員が対象となります。※事業者(社長)は雇用する側になるので加入できません。
>>> 勤労者財産形成事業本部
財形貯蓄の仕組み
財形貯蓄は、勤務している会社を通して金融機関にお金を預ける制度です。
財産作ることを目的とした制度ですから、貯めやすい、貯まりやすいをコンセプトに作られています。
給料天引きだから貯めやすい
財形貯蓄のメリットのひとつが「給料天引き」です。
つまり、給与が金融機関に振り込まれる時点ですでに、貯蓄分が引かれているのです。
口座にお金があるとついつい使ってしまったり、なかなか貯められない人には、ぴったりの制度です。
浪費家でも財形貯蓄なら大丈夫!
税金が優遇されるから貯まりやすい
財形貯蓄で貯まったお金は税金の面で優遇されています。ただし、財形貯蓄の種類によって扱いが違いますので注意が必要です。
財形貯蓄の種類
財形貯蓄は、貯蓄の目的によって、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3つに分かれています。
一般財形貯蓄とは
勤労者が金融機関などと契約を結んで、3年以上の期間にわたって定期的(毎月の給与、毎年のボーナスなど)に賃金からの控除(天引き)によって積み立てていく貯蓄です。
使用時の目的に制限はありません。加入に年齢制限もありません。
いつでも使える資金をためるのに適しています。
財形年金貯蓄
55歳未満の勤労者が金融機関などと契約を結んで5年以上の期間にわたって、定期的(毎月の給与、毎年のボーナスなど)に賃金からの控除(天引き)によって積み立てていく貯蓄です。
契約所定の時期(60歳以降の任意の歳)から5年以上にわたって年金として支払いを受けとることを目的とした貯蓄です。
老後の生活資金をためるのに適しています。
財形住宅貯蓄
55歳未満の勤労者が金融機関などと契約を結んで5年以上の期間にわたって、定期的(毎月の給与、毎年のボーナスなど)に賃金からの控除(天引き)によって積み立てていく貯蓄です。
持ち家取得を目的とした貯蓄です。
将来のマイホーム資金を貯めるのに適しています。
財形貯蓄の3つのメリット
財形貯蓄には3つのメリットがあります。
1.税制面が優遇される
一般的な貯金での税金
銀行など一般的な金融機関での利子には、原則として20.315%(所得税+腹腔特別所得税:15.315%と住民税5%)が課税されます(源泉分離課税)
財形貯蓄での税金
一般財形貯蓄に関しては、税制面の優遇はありません。一般的な貯蓄形態と同じ扱いになります。
財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄は、元利合計550万円までの利子に対しては非課税扱いとなります。※ただし貯蓄目的以外の払い出しを行うと課税されます。
※財形住宅貯蓄については。年金の支払いが終わるまで非課税措置が継続されます。
2.給料からの天引き制度
賃金からの控除(天引き)であるため、金融口座(給料口座)には、給与から貯蓄分が差し引かれて振り込まれます。
貯蓄分も含めて使いすぎてしまうことがないため、自然に貯蓄ができます。
3.財形好適融資制度が受けられる
あまり使う機会はないかもしれませんが、融資関係にもメリットがあります。
財形持家個人融資制度
財形貯蓄のいずれかに加入し、預け入れ残高が50万円以上、預け入れ期間が1年以上継続していること、最終預け入れから2年以内などの利用など所定の条件を満たせば、住宅購入・リフォーム・増改築に必要な資金の融資が浮受けられます。
融資額は50万円から財形預け入れ残高の10倍(最大4000万円)まで。ただし所要額の8割以内までという条件が付きます。
5年間の固定金利での融資です。
財形教育融資制度
雇用・能力開発機構の廃止に伴い2011年9月30日申し込み分で新規融資は中止となりました。
財形貯蓄のデメリット
天引きと税制面でお金のためやすい財形貯蓄ですが、デメリットもあります。
1.引き出しの制限
契約してから1年後から引き出しが可能となります。
一般財形に関しては、税金面での優遇措置はありません。その代わり加入してから1年が経てばいつでも引き出すことができます。契約は継続されます。
引き出すときは
- 全額引き出し
- 一部引き出し
- 全額引き出し+解約
から選べます。
※年金・住宅財形に関しては貯蓄目的以外で引きだすと、そこから5年間さかのぼって利息に課税されます。また、引き出すには「解約」が必要です。
2.すぐに振り込まれない
書類による手続きが必要なのですぐに引き出せません。また、経理を通しての処理になるため会社によっては引き出せる日が決まっていたり、時間がかかります。
3.退職した時、転職した時に解約する必要がある。
※転職先も財形貯蓄を取り扱っていれば継続することが可能です。
4.会社が採用した財形貯蓄によっては元本割れのリスクがある
ペイオフで保証される普通預金額が減る
金融機関が倒産したときに普通預金を補償してくれる預金保険(ペイオフ)の補償額は最高1000万円までですが、その中に財形貯蓄分も含まれます。
そのため、補償されるのは財形貯蓄と普通預金を足した1000万円までとなります。
結局、財形貯蓄はどうなの?
給与から天引きされる仕組みは、とても魅力的です。これなら貯められる!という人も多いのではないでしょうか。
しかし、税制面で優遇されるといってもバブルの頃と違い、利子はスズメの涙程度です。手数料であっという間にマイナスになる可能性もあります。
可能性は低いですが、元本割れや金融機関の倒産などのリスクもゼロではありません。住宅取得の融資も受けられますが、最近は銀行でも超低金利で借りることもできます。
貯金が苦手な人にはおすすめ
結局、天引きによって、貯金がしやすいというのが一番のメリットと言えそうです。自分で貯められる人にはあまりメリットがないかもしれませんね。